甍 iraka 賞
2012年 第2回 学生アイディアコンペティション
審査員講評
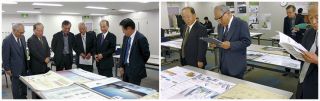
 |
森 暢郎 もり のぶお |
日本建築家協会 副会長 山下設計・特別顧問(前社長) |
|
|
昨年度に創設された甍賞学生部門の第2回目を、年度を空けずに迎えることができた。
このたびも力作揃いで、「復興と瓦」という今回の課題に真摯に取り組んでいる応募案だった。 日本瓦は、屋根葺き材などの機能材であり、同時に日本の美意識に通底する修景素材だ。 この瓦が震災復興で生み出すのは、土地固有の特徴が踏まえられた風景であり、被災地が元気になって笑顔が溢れる仕掛けである。 そして犠牲者への祈りと被災体験を後世に伝える仕組みであり、被災地に寄り添う日本的な振る舞いである。 審査では、委員一同が応募者を伏せた提案資料を基に厳正に審査して、金賞に「瓦を紡ぐ水景」を選んだ。 この応募案は、海と人の繋がりを大事にする堤防づくりで、堤の土盛りに瓦礫が利用され、瓦仕上げの円形の堤が幾重にも重なり段々状に築かれた防波堤の提案だ。 屹立するスーパー堤防ではなく津波の襲来をいなす「しなやか」な仕掛けであって、同時に震災記録の役割も担いながら海沿いの風景を再生するアイデアである。 銀賞の「ある港町の瓦碑(しるし)」は、津波到達高さを示す瓦屋根の記念碑づくりで、同時に甍が連なる集落再建と地域コミュニティ再生を目指す提案である。 次に銅賞の「記憶瓦」は、瓦積みの塔を津波被災エリアに点在させて津波到達高さやその範囲を伝える記録塔で、積み上げた瓦の隙間から日中だけでなく夜間も光が洩れる慰霊塔という提案だ。 いま一歩及ばずに佳作受賞となった応募案も、三賞受賞の応募案と近似した発想から発展させた特徴的なアイデア、 そして多色の丸瓦を使った棚田、陽の光の美しさが際立つ瓦の形状という優れた提案である。 これらの受賞提案が、技術的な可能性検証を必要とするものの復興策のヒントになればと願っている。 とは言え、被災地の瓦礫処理や瓦解した街や集落の再建など、本格的な復興に至っていない現状を思えば、一刻も早く地域の絆が復活して、瓦も活用された被災地の復興を願わざるを得ない心境である。 |
|
 |
栗生 明 くりゅう あきら |
日本建築家協会 栗生総合計画事務所 主宰 千葉大学大学院教授 |
|
|
3.11以降、我々の風景は変わった。いや正確に言うと我々の風景を見る目が変わった。
今までは先進的、近代的な町並み風景が、経済の発展を約束し、我々を幸福にしてくれそうに見えていた。
ここ20年の日本経済の停滞がこの風景を色褪せたものにしていたが、今回の地震、津波災害とそれに続く原発事故は、我々の風景を見る目に壊滅的な打撃を与えた。
被災地では慣れ親しんだ風景が瞬時に失われ、夥しい瓦礫の山が眼前にひろがった。 さまざまな復興プロジェクトが立ち上がっているが、風景について論じられているものは極めて少ない。 我々はどのような風景を取り戻したらよいのか。先日YouTubeをチェックしていたら、松岡正剛さんが「3.11と母国再生」というテーマで話をしていた。 「日本再生」ではなく「母国再生」である。「母なるもの」が問われていると言う。 杜甫の五言律詩に「国破れて山河在り」とある。母なる大地、母なる自然の懐にある安定した生活への回帰イメージがこの詩に読み込まれている。 近代化とは「父なるもの」の代名詞だったのではないか。 我々は資本主義社会が強要する大量生産、大量流通、大量消費のサイクルに絡め取られて、足元をおろそかにしていた。 伝統や文化や自然といった経済的指標にカウントされにくいファクターを意図的に忌避してきた。 風景にとって「母なるもの」は懐かしく帰りたくなる風景である。ひたむきに暮らす人々の温もりを感じさせる風景である。 自然景観のなかにしっくりと納まっている家や家並みの風景である。 瓦は土から生まれ土に帰る。瓦は母なる大地の表象として我々の身体に深く刻まれ、瓦が織り成す風景は郷愁をもって記憶される。 金賞「瓦紡ぐ水景」は、防災堤防を瓦礫の「再利用」と、瓦の「記憶の継承」に重ねるというストーリーが説得力を持ち、秀逸であった。 銀賞「ある港町の瓦碑」は津波到達ラインに復興のシンボル「みんなの屋根」を構築することで、自然に溶けこんだ「地域共同体再生の風景」として美しい。 銅賞「記憶瓦」は場所ごとの津波の高さを瓦の塔の高さとして点在させることで災害の記憶を風化させない。 入選作はいずれも瓦という素材の持つ、包み込むような暖かな「母なるイメージ」を、「記憶に残る風景」として昇華させていることが評価されたものである。 |
|